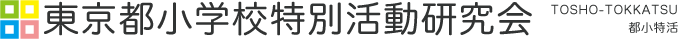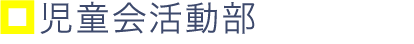
今年度の研究
部長 渋井 洋子(東久留米市立神宝小学校)
研究主題「自ら未来を切り拓く児童を育成する児童会活動」
令和6年度より新しい研究主題で研究がスタートしています。以下については、決まり次第掲載していきます。
1 主題設定の理由
2 研究の視点
3 研究構想図
児童会活動部メーリングリストへの参加登録
参加を希望される方は、下記のフォームに、「お名前」「メールアドレス」を入れて、「参加」ボタンを押してください。登録されたメールアドレスに「参加のご案内」のメールが届きます。そのメールから「登録完了URL」にアクセスすると登録が完了します。